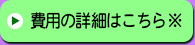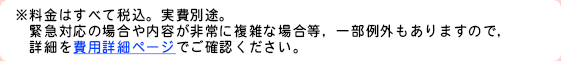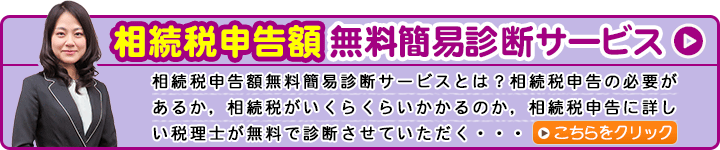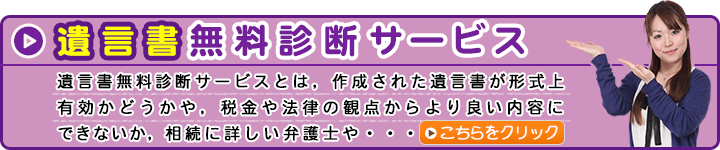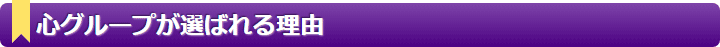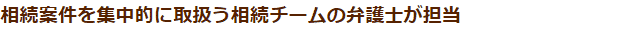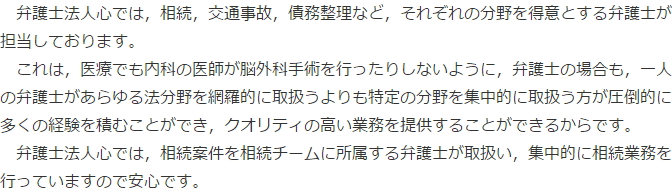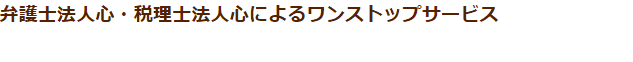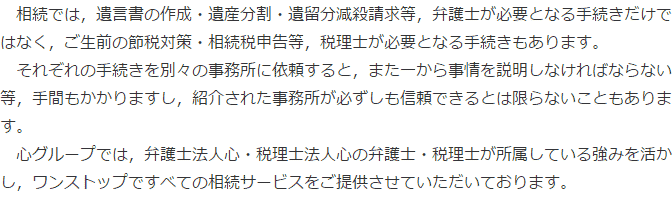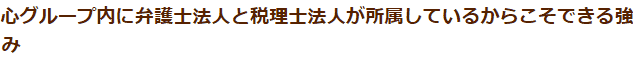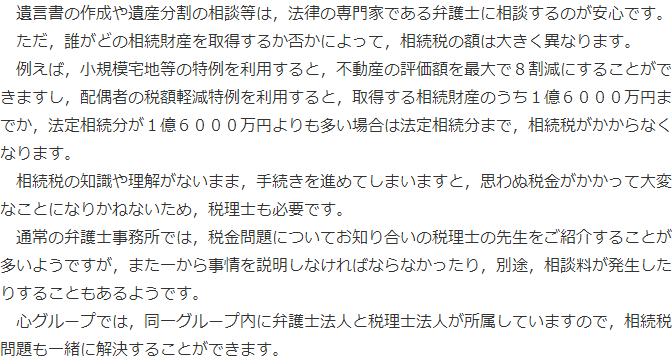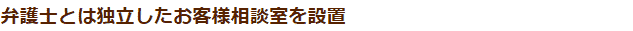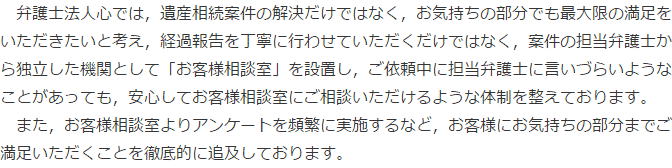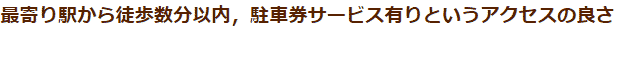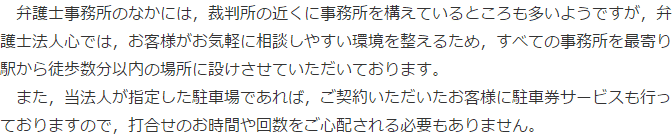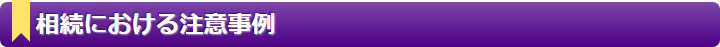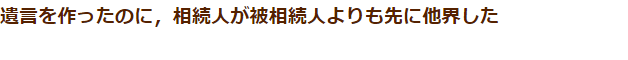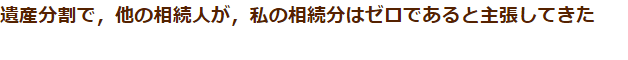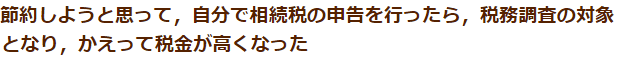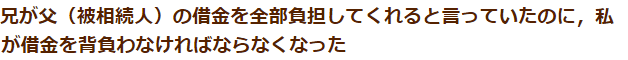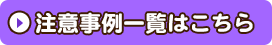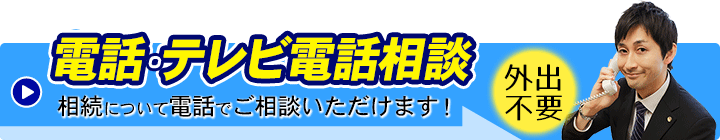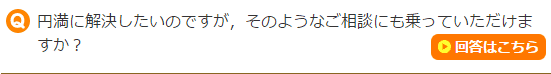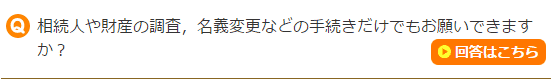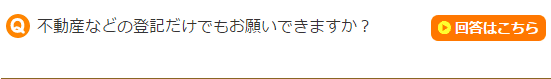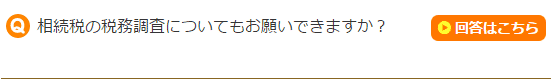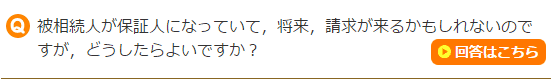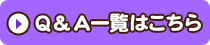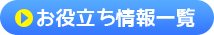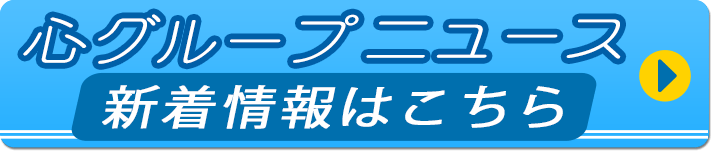業務内容
京都での相続に関するご相談について
当法人の相続のご相談に関する強みをまとめました。ご相談を検討する際の判断材料になると思いますので、参考にご覧ください。
相続の注意点
相続での注意点と、それぞれのケースの解決方法・予防のためのアドバイスをまとめました。京都の相続でも十分に起こり得ることですので、参考にしていただければと思います。
サイト内更新情報(Pick up)
2025年12月5日
相続登記
家の名義変更に関するQ&A
その家を相続することになった人が名義変更を行います。ある方が亡くなったとき、遺言書がない場合は、相続人同士で話し合い、まず誰がその家を相続するのかを決める必要があります。・・・
続きはこちら
2025年11月5日
相続放棄
相続放棄の必要書類
相続放棄には、以下の書類が必要となります。・亡くなった方の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・亡くなった方の住民票・相続放棄申述書・期限を経過している場合のみ:事情の説明資料・・・
続きはこちら
2025年10月10日
手続き
相続手続きに必要な書類
相続手続きにおいて最初に集めるべき必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本です。戸籍謄本を集めることで、相続人が誰であるのかを確定させることができます。相続人の漏れを防ぐ・・・
続きはこちら
2025年9月12日
遺留分
遺留分と生前贈与
遺留分は、遺産に対する最低限の権利です。まずはそれぞれどのようなものなのか簡単にご説明します。そのため、例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記されていたとして・・・
続きはこちら
2025年7月11日
遺産分割
遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、簡単にいえば、相続人同士で遺産を分けるための話合いを行うことを指します。亡くなった人が所有していた財産は、相続の発生により、原則として相続人全員で・・・
続きはこちら
2025年6月4日
遺言
遺言を作成するまでの流れ
遺言を作成するにあたって、メインになるのは、「誰にどの財産を相続させるか」ということです。その前提として、自分がどのような財産を保有しているのかを把握しておく必要が・・・
続きはこちら
2025年5月16日
相続税
相続税の基礎控除
相続が発生した場合、相続税を納める必要があるのではないかと心配される方は少なくありません。しかし、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の発生を心配する必要は・・・
続きはこちら
相続について詳しく知りたい方へ
相続に関するお役立ち情報の更新を随時行っております。用語の意味といった基本的なことから各種の対策など様々な情報を掲載しておりますので、ご一読ください。
所在地のご案内
京都駅から徒歩3分の場所に事務所がありますので、相続のお悩みのご相談にお越しいただきやすいかと思います。お越しいただく際には、こちらから所在地に関する情報をご覧ください。
相続において各専門家が協力できることの強み
1 1人の専門家では限界がある
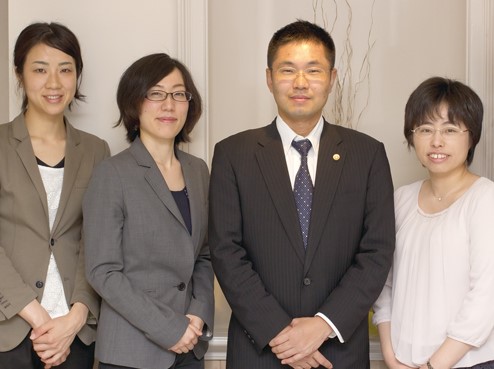
専門家であっても、何でも1人でできるとは限りません。
より高度な内容になればなるほど、分野は細分化されていきます。
例えば、町の病院では、眼科や内科といったように、分野が分かれ、医師はその分野を担当しつづけます。
では、相続の場面ではどうでしょうか。
相続の手続きを進めていくと、例えば遺産の中に不動産が含まれていた場合は相続登記が必要です。
このような場合は、相続登記に詳しい司法書士などの専門家の力が必要です。
また、相続の場面では、相続に関する税金の問題を検討する必要があるため、税理士の力も必要です。
さらに、相続人同士で、遺産の分け方で揉めてしまった場合は、紛争解決に対応できる弁護士が必要です。
このように、相続の場面でも、様々な分野の専門家が必要です。
2 同じ説明を何度もする必要がなくなる
様々な分野の専門家がそろっていたとしても、仮に、各専門家が連携していない場合は、どうなるでしょうか。
相続のことで困った方は、どの専門家に相談をすればいいかさえ、分からないことが多くあります。
特定の専門家に相談したとしても、その専門家が扱っていない分野については、他の分野の専門家に相談するよう促されるのが通常です。
その結果、相続のことでお困りの方は、いくつもの専門家の事務所を訪れ、何度も同じ説明をしなければならなくなります。
最初から、各専門家が協力している事務所に相談すれば、必要となった際に各専門家同士で情報を共有し、適切な対処が可能なため、何度も同じ説明をする必要はありません。
3 スピーディーな解決が可能
相続では、共通して使用する資料があります。
例えば、戸籍謄本などはその最たる例です。
各分野の相談を別々の専門家に依頼していると、各専門家が業務で使う戸籍謄本などの資料を取り寄せることになるため、時間がかかってしまいます。
各専門家が協力して資料を共同で利用することができれば、資料を集めるための時間を大幅に短縮し、よりスピーディーな解決が可能になります。
私たちは、各分野の専門家がすぐに連携できる体制を整えているため、よりスムーズに相続を進めたり問題解決ができたりするかと思います。
京都駅の近くにも事務所を構えていますので、京都で相続が発生した方は、私たちまでご相談ください。
相続の無料相談をお考えの方へ
1 専門家の相続の実績をチェック

相続のお悩みごとがある場合、どの専門家に相談したらよいか分からない場合もあると思います。
専門家といっても、力を入れている分野はまちまちなので、相続の相談をしたい場合、当然のことながら、相続の実績があるところを探すとよいでしょう。
相続に力を入れている専門家であれば、扱っている案件のほとんどが相続案件であるというケースもあります。
そういった相続の実績が豊富な専門家であれば、蓄積した相続に関するノウハウによって、適切なアドバイスを受けられることを期待できます。
一般的に、相談は有料であることが多いのですが、無料で応じている場合もあるので、そのような機会を生かして、相続の実績についてしっかりとチェックすることをおすすめします。
無料相談のときに得られたアドバイスのみで、解決できるような場合もありますが、一部の知識だけを得て進めてしまうと、かえって全体としては適切ではないということもあります。
そこで、無料相談の機会を生かして、全体として解決ができるかどうかを、しっかりと見極めるとよいかと思います。
2 法律と税金両方のサポートを受けられるかをチェック
相続手続きにおいては、相続に関する法律や判例に則って進めることはもちろんですが、税金についても対策が必要です。
もし税金の面での見落としがあると、本来支払わなくてもよかった税金を支払わなければならなくなるおそれがあります。
例えば、相続発生後は、ご生前の収入や遺産の額に応じて、税金の申告が必要になります。
この申告には期限が設定されているため、遺産の分け方などに集中してしまい、申告の期限を過ぎると、余分に税金を支払うことになってしまう場合があります。
また、遺産の分け方の方法によっては、税金を軽減するための制度を使えなくなる場合もあります。
このように、相続の場面では、法律に関するサポートと税金に関するサポートは、車の両輪のような関係にあり、どちらか一方が欠けると、大きな不利益が発生する可能性があるのです。
そのため、無料相談では、その専門家の元で、法律と税金両方のサポートを受けることができるのかを確認するとよいかと思います。
3 専門家の人柄もチェック
相続は、単純に財産だけの話では終わりません。
家族だからこそ、思い入れが生じることもあり、人間関係や感情にもかかわるところが多いと思います。
そのため、専門家が自分の思いを汲んでくれるかどうかも、大切なチェックポイントとなると思います。
専門家は、たとえば、相談者と相手方とのあいだで、感情面での対立があったとしても、相談者の感情面をそのまま主張するとは限りません。
むしろ、法的な主張の中で、きちんと位置付け、構成することが求められます。
しかし、そうかといって、相談者の思いを何も汲んでくれないのであれば、法的には正しくても、本当に分かってもらえているのかと不安・不満に思われるかもしれません。
実際のところ、専門家が、相談者の思いを汲んだうえで、法的に適切に対処してくれるのであれば、相談者とのやりとりでも、相手方との交渉でも、うまく進行すると思われます。
この点は、相性によるところが大きいといえます。
相性は実際に話をしてみて、会話のテンポや受け答え、事案に対する姿勢、振る舞いなどから推し量ることができるかと思います。
無料相談の場を活用し、専門家がどのような人柄であるのか、自分との相性が良いかについて、確認するとよいかと思います。
遺留分を請求したい方へ
1 遺留分の請求権には時効があります

遺留分を請求する場合、「遺留分の請求ができると知ってから1年」という期限があることに注意が必要です。
もし、遺留分の請求期限である1年が過ぎてしまうと、遺留分を請求できる権利は時効によって消滅してしまいます。
そのため、遺留分の請求をする場合は、速やかな対応が必要です。
2 遺留分の額は遺産の評価によって大きく変わることも
遺留分がいくらなのかを計算する際は、まず遺産の総額をはっきりさせる必要があります。
しかし、遺産の総額というのは、そう簡単に数字が出るとは限りません。
例えば、遺産の中に不動産がある場合は、その不動産を何円の財産と考えるべきなのかは、非常に難しい問題です。
不動産の評価額は、専門家によっても見解が異なることもあるため、交渉を有利に進めるためには、不動産に関する知識やノウハウも必要になってきます。
3 生前贈与が遺留分に影響を与えることも
仮に、長男に対し5,000万円の生前贈与がなされたために、遺産が200万円しかないような場合は、どうなるでしょうか。
遺留分の額が遺産総額によって決まるとはいえ、この200万円を基準に遺留分の計算をしても、長男とそれ以外の人との間でもらえる金額に不平等が生じてしまいます。
そこで、一定の場合には、生前贈与も遺産とみなすことになっています。
反対に、遺留分を請求する側が、多額の生前贈与を受けている場合、遺産の一部を先にもらったとみなされるケースもあります。
そういったケースでは、請求できる遺留分の額が下がることがあります。
このように、生前贈与は、遺留分に大きな影響を与えます。
そのため、遺留分を請求する場合は、生前贈与の有無についても、調査が必要です。
4 遺留分の計算は専門家にお任せください
遺留分の計算方法は、民法に記載されていますが、とても複雑な記載になっているため、計算するのは簡単ではありません。
遺留分の請求を検討している方は、まずはご相談ください。
遺留分がどれぐらいあるのかを含め、遺留分侵害額請求はどのように進めるのか等、遺留分に関する疑問・不安について、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 生前対策の2つの柱

生前対策には、紛争の防止対策と、税金の対策の2つの柱があります。
紛争の防止対策をしっかりしておかないと、ご家族が遺産の分け方で揉めてしまい、最終的には裁判にまで発展してしまうようなケースがあります。
また、税金の対策をしっかりしておかないと、残された家族に税金が課された場合に、遺産の中から税金を支払うことができないと、残された家族が苦労することになってしまいます。
生前対策をする場合は、この2点についての対策を重点的に行うことが大切です。
2 紛争防止対策をしなかった場合の例
何も対策をしないまま、相続が発生した場合は、残された家族が遺産の分け方を話合いで決めることになります。
その際、例えば、長女が同居して介護をしていた場合、長女は遺産を多めに欲しいと主張するかもしれません。
その他のケースとして、長男が大卒なのに、二男が高卒だった場合は、二男が大学の学費分は遺産を多めに欲しいと主張するかもしれません。
さらに、遺産の多くが不動産で、あまり預貯金が無い場合、不動産の分け方をめぐって、意見が合わない可能性が高くなります。
このように、生前に何も対策をしないまま相続が発生した場合は、残された家族が揉めてしまう火種が、至るところに隠れています。
3 税金対策を何もしなかった場合の例
一定以上の遺産がある場合は、相続に関する税金を納める必要があります。
しかし、税金は現金で納めなければならないため、例えば、遺産の多くが不動産で、預貯金の割合が少ない場合は、相続人が自分の資産から税金を用意しなければいけなくなります。
もし、相続人が自分の資産から税金を用意できない場合は、相続した遺産を売却して支払うことになりますが、うまく売却できない場合は、業者に安く買いたたかれてしまうこともあります。
税金対策として、節税を考えるとともに、納税資金の確保も考えることが大切です。
4 法律と税金の両方の専門家にご相談ください
生前対策では、紛争防止対策と、税金対策が必要です。
そのためには、相続の法律に関する専門家と、税金に関する専門家が協力して、生前対策を行うことが重要です。
したがって、生前対策を検討されている方は、各専門家が協力し合っている事務所を中心に、相談先を検討することをおすすめします。
相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄はすぐに行動しないと間に合わない場合も

相続放棄をすれば、相続人としての地位を失うことになるため、亡くなった方の債務を受け継がなくてもよくなります。
しかし、3か月という期限があるため、すぐに行動しなければ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
2 スピーディーな対応が可能な専門家にご相談を
もし、亡くなった方が何百万円もの債務を抱えていた場合、相続放棄ができなければ、その債務を背負わなければならなくなってしまいます。
そういった事態を避けるためには、何としてでも相続放棄を成功させなければなりません。
しかし、大きな障害となるのが、期限の問題です。
3か月という期限に間に合わせるためには、多くの相続放棄の実績があり、スピーディーな対応ができる専門家に相談することが大切です。
3 遺産を処分すると相続放棄ができなくなるかもしれません
相続放棄をすると、相続人としての地位を失います。
そのため、遺産を処分する権限もなくなり、遺産に手を付けることができなくなってしまいます。
例えば、亡くなった方の預金を払い戻したり、亡くなった方の遺品を業者に売却したりした場合は、「遺産を相続した上で、遺産の処分を行った」とみなされるため、相続放棄ができなくなることがあります。
このように、相続放棄を検討している場合は、「やってはいけないこと」というものを、あらかじめ知っている必要があります。
4 相続放棄に詳しい専門家へのご相談がおすすめです
上述したように、相続放棄では、遺産の処分など「やってはいけないこと」に関する理解が重要です。
しかし、この「やってはいけないこと」については、はっきりと回答できる専門家は多くありません。
その理由は、何が「やってはいけないこと」なのかが、法律で明確に記載されていないためです。
したがって、過去の裁判所の判断や、専門家自身が実際に扱った案件等から、「やってはいけないこと」に関して十分に検討することが必要となります。
相続放棄について専門家に相談する際は、その専門家が「やってはいけないこと」について、十分な理解があるのかもチェックすることが大切です。
遺言についてお悩みの方へ
1 遺言の落とし穴

遺言を残しておけば、誰にどのような財産を相続させるかを、あらかじめ指定しておくことができます。
しかし、遺言の書き方には、細かいルールがあるため、専門家のアドバイスなしで遺言の作成を行っても、無効になってしまう可能性があります。
また、遺言によって、残された家族が揉めないようにしたつもりが、遺言の内容が不適切であったため、むしろ揉め事を助長してしまうということもあります。
2 揉め事を助長してしまうかもしれない遺言の例
⑴ 年齢順に亡くなるとは限らない
例えば、Aさんが、長男と二男に遺産を半分ずつ相続させるという旨の遺言を残したとします。
Aさんが亡くなった場合は、長男と二男が遺産を半分ずつ相続することになりますが、もし、長男がAさんより先に亡くなってしまった場合は、手続きが複雑になります。
長男が先に亡くなった以上、長男に渡すはずだった遺産の半分はもらい手がいなくなるため、この部分をめぐって、相続人同士で争いが起きてしまうかもしれません。
年齢順に亡くなるとは限りませんので、そのことも想定して対策しておく必要があります。
⑵ 全財産を1人に相続させると紛争の火種に
介護などでお世話になった人に、全財産を相続させたいとお考えになる方は少なくありません。
しかし、そういった遺言を残すと、紛争の火種になることがあります。
例えば、同居してお世話をしてくれた長女に全財産を相続させ、二女には遺産を渡さないという旨の遺言書を残した場合、二女には一定の金銭を長女に請求できる権利が発生します。
ですが、その金額で折り合いがつかないと、裁判にまで発展することがあります。
遺言を作成する際は、遺留分にも配慮しておくとよいかと思います。
3 遺言は専門家にご相談を
このように、遺言は適切な専門家によるアドバイスがなければ、かえって揉め事を招いてしまいかねないものです。
何のために遺言を作成するのか、どのようなことを実現したいのかによって、遺言の記載内容は変わります。
そのため、遺言を作成する場合は、適切な専門家に相談をすることが大切です。
また、遺言はいつでも書き直すことができるため、ひとまず早く作っておいて、随時修正をしていくということも可能です。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 法律を知らないと損をする可能性も

遺産分割は、亡くなった方の財産を、相続人で分け合う手続きです。
原則として、遺産とは亡くなったときに存在している財産を指しますが、生前贈与などがある場合は、例外的に生前贈与も遺産とみなされる場合があります。
また、亡くなった方の介護をしていた場合には、遺産の分け方を決定する際に介護の貢献度が考慮されることもあります。
こういった法律の知識がなければ、本来なら取得できたはずの遺産を、取得できなくなるおそれがあります。
2 遺産分割はスピードも大切
遺産分割をする場合、生前贈与を含め、遺産に関する資料を集める必要があります。
しかし、資料は時間の経過とともに失われていくものですので、早い段階で遺産分割の手続きを進めなければなりません。
また、祖父母の遺産分割をしないまま、何十年も不動産の名義を変えていないというケースもあります。
しかし、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、登記をしないまま定められた期限を過ぎてしまうと、過料が科せられることとなりました。
そのため、上記のように、遺産の中にこれまで放置されていた不動産が含まれている場合にも、期限までに遺産分割をしなければならなくなります。
3 遺産分割では税金にも注意が必要
遺産の分け方次第で、相続に関する税金が大きく変わることがあります。
例えば、配偶者が遺産を相続した場合、1億6000万円までは相続に関する税金がかからないといった特例があるため、配偶者が取得する遺産の割合を増やすと、一旦は税額を抑えることができます。
もっとも、次にその配偶者が亡くなった時は、税額が高くなってしまうこともあるため、次の相続を見据えた上で、遺産の分け方を決める必要があります。
4 法律と税金両方に強い専門家にご相談を
遺産分割で大切なのは、専門的知識とスピード、そして税金面の対応です。
専門的知識やスピードを求めるなら、相続を集中的に取り扱っている専門家に相談することが大切です。
また、税金面での対応も重要なため、遺産分割で専門家に相談する場合は、税金面の専門家と連携をしているかどうかも確認するとよいと思います。
遺産分割においては、相続人や相続財産の調査を行い、それらを明確にすることも大切になってきますので、少しでも不安があるようでしたら、まずは一度ご相談ください。
相続税についてお悩みの方へ
1 相続税申告の期限は短い

相続税の申告には、10か月という期限が定められています。
「10か月もあるなら、何とかなりそう」と思うかもしれませんが、申告のためにしなければいけないことは多く複雑なため、相続税の申告を期限内にできないおそれがあります。
もし、期限内に相続税の申告が出来なかった場合、追加で税金を納めなければならなくなるため、注意が必要です。
以下では、相続税の申告期限内に対応しなければいけないことについてご説明いたします。
2 10か月の間にやらないといけないこと
⑴ 遺産の調査
相続税は、遺産に対して税金が課せられるため、遺産の内容の調査が必要です。
しかし、亡くなった方がどのような遺産を持っていたかは、ご家族であってもよく分からないことがあります。
どの金融機関に口座を持っているのか、株を保有しているのかなどは、家の中の通帳を見れば、ある程度は分かります。
しかし、今は通帳がない金融機関も増えてきたため、しっかりと調査をしておかないと、遺産の全容を把握することはできません。
また、不動産についても調査をする必要があります。
亡くなった方が単独名義で所有していた不動産であれば、毎月、固定資産税の通知が届くため、ある程度目星はつきます。
しかし、共有名義になっている不動産は、代表者にしか通知が届かないため、家の中を調べても資料が見つからない可能性があります。
⑵ 遺産の分け方の決定
誰がどの遺産を取得するのかを決めないと、相続税の額も決めることができません。
そのため、遺産の分け方も、この10か月の間に決める必要があります。
基本的には、まずは話し合いで遺産の分け方を決めて合意を目指します。
話し合いがまとまらず、もしも遺産の分け方で揉めてしまった場合は、裁判所で分け方を決めることになる可能性があります。
裁判所で遺産の分け方を決める場合、1年以上決着がつかないことも珍しくありません。
⑶ 相続税の納付
10か月以内に、相続税の申告だけでなく、相続税の納付まで行う必要があります。
相続税は現金で納めなければならないため、例えば、遺産の大部分が不動産で預貯金がない場合は、不動産を売却するなどして、相続税を納めなければなりません。
3 相続税のご相談はお早めに
相続税の申告期限である10か月は、あっという間に過ぎてしまいます。
余計な税金を支払うことを防ぐためにも、専門家への相続税のご相談はできるだけ早く行うことが大切です。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 以下に該当する場合はお早めにご相談ください

相続問題は、様々な種類がありますが、以下のケースに該当する場合は、お早めに専門家にご相談いただくとよいかと思います。
⑴ 生前対策を検討している場合
⑵ ご両親がご高齢の場合
⑶ 相続が発生した場合
2 生前対策を検討している方へ
生前対策は、いつでもできるというわけではありません。
生前対策をする場合、今の財産状況を把握しつつ、今後発生するであろう生活費や介護費、医療費などを計算し、誰にどのような財産を残すのか決める必要があります。
つまり、上記のことを考慮して適切に対策を行う必要があるため、生前対策は、病気になったり、高齢のために判断能力が低下したりしてしまった後では、難しい場合があるのです。
さらに、生前対策は、場合によっては、10年以上時間をかけて行うものもあります。
そのため、生前対策を検討している方は、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。
3 ご両親がご高齢の方へ
ご両親がご高齢の場合、今後施設などに入ることも検討しなければならないかと思います。
しかし、施設に入るためには、多額の入居一時金を納めたり、毎月の施設利用料などを支払ったりする必要があります。
その費用を捻出するための有効な方法として、もう戻る予定がない自宅を売却するという方法があります。
もっとも、自宅の売却は、判断能力が低下した後だと、難しい可能性があります。
そこで、財産の管理権を子どもに渡しておくという手続きを、事前に行っておく必要があります。
この手続きは、当然ながら判断能力が低下した後で行うことは、難しいケースが多いため、できるときにしておかなければなりません。
4 相続が発生した方へ
ご家族が亡くなった後は、お葬式や四十九日などで、慌ただしいことが多いですが、相続の手続きは、相続発生後すぐにとりかかることが大切です。
例えば、もし亡くなった方に借金があった場合、相続の権利を放棄する手続きを裁判所で行わないと、その借金を相続人が背負うことになってしまいます。
この手続きの期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められているため、非常にスケジュールは厳しいものとなります。
相続人や相続財産の調査に時間を要することもありますので、余裕をもって対応できるように、早めに相続手続きに着手することをおすすめします。
このように、相続の手続きには、期限が設定されているものがあるため、相続発生後はなるべく早めに専門家に相談することが大切です。
相続のご相談から解決までにかかる時間
1 相続人同士で揉めている場合は数年以上かかることも

相続人同士で揉めている場合の典型例として、遺産の分け方で折り合いがつかないというケースがあります。
例えば、父が亡くなり、長男と二男が遺産を分け合う際に、長男と二男がいずれも「実家を相続したい」と主張するなど、『欲しい遺産が同じものになってしまった場合』があり得ます。
お互いに納得できる落としどころを見つけなければいけませんが、感情的になってしまい冷静な話し合いが難しくなると、当事者だけでの解決が困難となってしまいます。
また、長男が「次男は多額の生前贈与をもらっているから、遺産の取り分を減らすべきだ」と主張するなど、生前の事を考慮すべきという意見の対立も起きやすい揉めごとです。
こういったケースでは、最終的には裁判所での手続きが必要になることもあり、長ければ数年以上の時間がかかることがあります。
2 揉めていない場合は数か月以内の解決が可能です
相続人同士で、特に意見の相違は無く、相続の手続きを淡々と行っていく場合であれば、すべての手続きが数か月以内に終わるケースが多いと思われます。
例えば、相続手続きの代表例として、預貯金の解約があります。
預貯金の解約は、銀行所定の用紙に署名・押印をした上で、戸籍や印鑑証明などの必要書類を銀行に提出する手続きです。
戸籍等の必要書類を集めることさえできれば、2か月以内に手続きが完了するケースがほとんどです。
また、相続手続きの代表例として、不動産の名義変更があります。
不動産の名義変更は、法務局で行う手続きですが、提出書類は銀行に出すものとあまり変わりません。
3 実際のスケジュール
⑴ ご相談
まずは、事務所にお越しいただくか、お電話でお話をお伺いします。
ご相談時に、今問題になっていることを明らかにして、法的にどのような過程で解決していくのかについて、ご説明いたします。
⑵ 相続人の調査
ご依頼いただいた後は、相続人の調査を行います。
具体的には、戸籍謄本を集め、相続人の人数を確定させます。
親子の相続であれば、取得しなければならない戸籍謄本が少ないため、3週間ほどで調査が終わることが多いですが、兄弟の相続などの場合は、集める戸籍が多くなるため、1か月半ほどの時間がかかる場合があります。
⑶ 相続財産の調査
遺産の分け方が決まった後に、新たな遺産が見つかると、手続きをやり直さないといけないことがあります。
そのため、遺産を分ける話合いをする前に、どれくらいの相続財産があるのかをはっきりさせる必要があります。
具体的には、亡くなった方が残した通帳などをヒントに、銀行などで残高証明書を取得したり、役所で不動産の有無を調査したりします。
遺産に関する資料が残っていれば、1か月から2か月程度で調査は終わりますが、全く手掛かりが無い場合は、調査に3か月以上かかることもあります。
⑷ 遺産の分け方の協議
相続人全員で、遺産の分け方の協議を行います。
もし、相続人同士で意見の対立が起きてしまった場合は、この協議で何年もかかる場合があります。
反対に、相続人同士の意見がすぐにまとまれば、すぐに協議は終わります。
相続対策と専門家
1 相談相手が本当に相続対策の専門家なのか、注意が必要です

今までは、「相続対策なんて、自分には無関係」、「うちの家で争いなんて起きないから大丈夫」と考えてしまいがちな方も多くいらっしゃいましたが、近年は、終活ブームもあり、相続対策が話題になっています。
相続対策には色々な分類方法がありますが、最も重要な項目は、3つあります。
1つ目は、紛争防止対策です。
紛争防止対策とは文字どおり、相続人同士が遺産の配分や遺産の分け方を巡って争ってしまうのを防ぐことを指します。
2つ目は、相続税対策です。
一定以上の資産を持ったまま亡くなると、相続税の申告と納税が必要になりますので、納税資金の用意や相続税の軽減措置が必要です。
京都府内では、令和4年分の件数として、被相続人3423人分の相続税申告がなされたという統計があります。
参考リンク:国税局・相続税の申告事績(京都府計)
3つ目は、お葬式・お墓関係の対策です。
どのようなお葬式をするのか、お墓を誰が受け継ぐのか、ご遺骨をどうするのかなど、亡くなった後の手続きについて事前に決めておくことが大切です。
こういった相続対策の需要増加に目をつけ、京都でも様々な業者が相続対策に関連したサービスの提供を行っています。
しかし、その業者が本当に適切な相続対策の専門家といえるかは、十分な注意が必要です。
もし、法的に間違ったアドバイスや、税金面を考慮していないアドバイスをされた場合、予想外の不利益を受けてしまうおそれがあります。
2 実際にあった例
相続対策の1つに、マンションを建築して貸し出すというものがあります。
このようにすることで相続税を安くすることができると、雑誌などで特集が組まれ、そういった情報に特化した書籍も発売されています。
たしかに、一般論として、現金を3億円持っているよりは、3億円でマンションを建築して貸し出した方が、相続税が安くなる場合があり、有効な方法となり得ます。
しかし、とある金融機関のすすめで、資産家がマンションを建築し、相続税を節税しようとしたところ、国側から訴訟を提起され、納税者側が敗訴したという事例があります。
このように、法律や税金の専門家が関与せずに相続対策を行うと、裁判を起こされて敗訴し、結局多額の税金を納めることになる可能性があります。
3 相続対策では、法律と税金の専門家の関与が不可欠です
相続対策では、遺族が揉めないための対策と、遺族が税金を納めることができるようにしておく税金対策が重要です。
このうち、遺族が揉めないための対策を適切に行うのは、実際に遺族が揉めた例を多数扱っている法律の専門家の関与がなければ、難しい場合があります。
なぜなら、遺族が揉めた場面を実際に扱っていないと、「どういったケースであれば揉めてしまうのか」が分からず、専門書に書いてある情報だけ根拠に、対策をしてしまうためです。
しかし、専門書に書いてある情報は、あくまで世の中で起きている揉めごとの、ごくごく一部を抜粋したに過ぎません。
そのため、実際の紛争を多数扱っている専門家の知見が重要なのです。
他方、遺族が税金をきちんと納めることができるよう、準備しておくためには、税金の専門家のアドバイスが大切です。
もし、税金の専門家が関与していない状態で相続対策を行うと、先ほどの例のように、余計に税金を支払うことになってしまう可能性さえあります。
そのため、相続対策を行う場合は、法律と税金の専門家が連携をとれている事務所に相談することが何よりも重要です。
4 相続対策は私たちにご相談ください
私たちは、相続を集中的に扱っている弁護士や税理士が連携して、相続対策を行っています。
そのため、専門書の中の知識だけでなく、これまでの事例も踏まえ様々なリスクを想定した上で相続対策をご提案することが可能です。
京都で相続対策をお考えの方は、ぜひ原則無料の相談をご利用ください。
相続人の調査が必要な理由と対応方法
1 相続人の調査が必要な理由

遺産分割協議を行うためには、ほかの相続人に連絡をする必要があります。
また、相続人がそろっていない状況で合意をしてしまうと、その合意内容は無効になってしまうので、相続人が誰であるかは、正確に確認する必要があります。
そのため、相続に関するご依頼を受けた場合は、まず相続人を調査することから始めます。
相続人に漏れがないように、相続人の調査をしっかりと行い、相続人を明確にします。
2 相続人の調査方法
相続人の調査は、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を集めることによって行いますが、これは慣れていないと、かなり時間がかかってしまうことがあります。
専門家は、職務上の特別な権限により、相続人を明らかにするために、戸籍謄本を集めることができるので、相続人の調査についても相談するとよいでしょう。
また、法改正により、本籍地以外の市区町村役場でも、本人が窓口に行けば、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)の戸籍謄本を取得できることとなり、戸籍の収集が便利になりました。
そうはいっても、戸籍の附票や兄弟姉妹の戸籍など、取得できないものもあるため注意が必要です。
そこで、相続人の調査については、必要に応じ、専門家と相談して役割分担を決めながら、効率的に進めるとよいでしょう。
3 必要な戸籍謄本
⑴ 共通して必要な戸籍謄本
どのような場合であっても、必要となるのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。
これらの戸籍謄本によって、亡くなった方の第1順位の相続人である子の人数を明らかにすることができます。
配偶者は、亡くなった方と同一の戸籍に入っているので、同時に取得できることになります。
⑵ 第1順位の相続人の調査
亡くなった方に子がいることが分かった場合、子の現在の戸籍謄本を取得します。
これにより、子が現在も存命中なのかどうかを確定させることができます。
子がすでに亡くなっている場合は、子の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、亡くなった方の孫がいないかを調査します。
もし孫がいれば、孫は第1順位の相続人となります。
⑶ 第2順位の相続人の調査
上記の調査により、第1順位の相続人がいないことが確定した場合は、第2順位の相続人である、亡くなった方の両親や祖父母の、現在の戸籍謄本を取得します。
⑷ 第3順位の相続人の調査
第2順位の相続人である両親や祖父母が、すでに亡くなっている場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、亡くなった方の兄弟姉妹の人数を確定させます。
兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、亡くなった方に甥や姪がいるかどうかを調べます。
つまり、甥や姪は、第3順位の相続人という立場となります。
相続について税理士に相談するタイミング
1 生前の対策を検討している場合

相続が発生した場合、受け継ぐ遺産の金額によっては相続税が課せられる可能性があります。
相続税は、遺産が多ければ多いほど高くなるため、相続税をできるだけ低く抑えるためには、相続発生時に、遺産を少なくしておくことが大切です。
その方法として、生前贈与を行う方も多くいらっしゃいますが、生前贈与の方法を間違うと、多額の贈与税が課せられてしまうことがあるため注意が必要です。
また、不動産の購入や売却によって、相続対策を行うケースもありますが、その場合も税金の話が出てきます。
このように、生前の対策を行う場合、様々な税金を考慮しなければなりません。
また、相続発生が近い状況では、できる対策には限りがありますので、生前の相続税対策について税理士に相談する場合、可能な限り早い段階で相談することが大切です。
2 相続発生後の場合
相続が発生した場合、以下の手続きが必要になるため、できるだけお早めに税理士に相談することをおすすめします。
特に、期限に間に合わなかった場合は、余分に税金を納めなければならない可能性もあるため、注意が必要です。
⑴ 相続人の調査
相続人が何人いるのかを確定させる必要があります。
「家族構成なんて、調べるまでもなく分かっている」という方もいらっしゃいますが、戸籍を調べてみると、前妻との間に子がいたり、認知している子がいたりするなど、誰も知らなかった相続人が見つかることもあります。
そのため、相続人が何人いるのかを改めて調査することが必要だといえます。
⑵ 相続財産の調査
預貯金、不動産、株式等、どのような遺産があるのかを調査する必要があります。
その財産の総額によっては、相続税の申告が必要になることもあります。
⑶ 遺産分割協議
誰がどの遺産を取得するのかを、早い段階で決めなければなりません。
特に、遺産の分け方によっては、相続税の総額が大きく変わる可能性もあります。
税金の観点からも、どのような遺産分割が適切か検討することが大切です。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 国家資格を持つ専門家に相談するのがおすすめです

相続に関わる資格として、様々な国家資格があります。
相続は、裁判所や法務局、税務署などで、複雑な手続きが必要になるケースがあり、こういった手続きは、国家資格を持った専門家でなければ、行うことができないものが多くあります。
その理由は、相続という分野は法律や税金の問題が絡み合い、それぞれに関する高度な専門性が求められるためです。
もし、法律や税金に詳しくない人がずさんな業務をしてしまうと、結果として、ご依頼者様の利益が失われることになりかねません。
そこで、相続に関する多くの手続きは、国家資格を持つ者しか扱うことができないよう、法律で定められています。
2 民間資格者に相談するときの注意点
日本では、相続に関わる多くの民間資格もあります。
民間資格者は、国家試験に合格したわけではないため、必ずしも法律や税金について詳しいとは限りません。
また、民間資格者は、裁判所や法務局、税務署などでの手続きを行うことができないため、結局は国家資格を有する専門家に相談をしなければならないというケースも珍しくありません。
そのため、民間資格者に相続の相談をする場合は、こういった点を踏まえて、相談をする必要があります。
3 国家資格者が連携をとれる専門家を選ぶのがおすすめです
相続は、法律や税金等、複数の分野を同時に解決する必要があります。
そのため、国家資格を有する専門家1人に相談すれば、すべて解決できるとは限りません。
各分野の専門家が必要に応じて連携できる体制を整えているところであれば、相続のトータルサポートが可能であるため、ワンストップですべての相続サービスを受けられるかと思います。
4 相続専門のホームページがある専門家を選ぶのがおすすめです
多くの専門家が、事務所のホームページを作成しています。
ホームページの構成としてよく見受けられるのは、ホームページの中の「取扱業務」の中に、「相続」という言葉が記載されているケースです。
これだけでは、相続に注力しているのかどうか判断できません。
こういった事務所と異なり、相続に特に力を入れている事務所では、事務所のホームページとは別に、相続専用のホームページを作成しているというケースもあります。
ホームページは、専門家がご相談者様に対して、情報を発信するツールであるため、相続専用のホームページを作成しているということは、それだけ相続分野に力を入れている可能性が高いといえます。
そのため、相続の相談をする場合は、その事務所が、相続専門のホームページを作成しているかどうかを確認してみるのもよいかと思います。
相続財産の調査方法
1 調査の前提としての相続人であることの証明

相続財産の調査は、つまり亡くなった方の財産の調査です。
通常、自分以外の財産を調査することは、たとえ家族であっても、プライバシーの観点からできません。
しかし、相続人は遺産を相続しているため、相続人にとって遺産の調査は、自分の財産の調査であるといえます。
そのため、相続人は遺産の調査をすることができますが、その前提として、まずは自身が相続人であることを証明する必要があります。
相続人であることの証明は、戸籍謄本を使って行うことになりますが、必要となる戸籍謄本を判断して各種の戸籍を集める作業は、慣れない方にとっては簡単なことではないかと思います。
専門家へのご依頼もご検討ください。
2 預金の調査
遺産の中で、最も重要な情報は預金の情報です。
預金以外にも、株式や不動産等の様々な種類の財産がありますが、預金の履歴を見れば、引落としの形跡などから他の財産が芋づる式に判明することもあります。
そのため、相続について詳しい弁護士であれば、まずは預金の調査を行います。
もっとも、預金の調査は、簡単なものではありません。
様々な金融機関の預金を一括して管理している機関はないため、預金の調査をする場合、それぞれの金融機関の預金を1つ1つ調べる必要があります。
通帳などの手がかりがない場合は、亡くなった方の住居、職業、生活圏などから、どの金融機関に口座を持っていたかを推測する必要があります。
また、遺言書によって、預金の名義が既に変わっているような場合は、預金の情報の開示を拒否されるケースもあります。
そのようなケースであっても、弁護士であれば、弁護士会を通じて、それぞれの金融機関に情報を開示させることが可能なため、預金の調査もスムーズに進みます。
3 各種専門機関への情報開示
上場している株式や、消費者金融などからの借金については、それぞれ特定の機関が一元的に管理しています。
相続財産調査に慣れている専門家であれば、これらの機関に頻繁に情報開示の手続きを行っているため、スピーディーに情報を集めて、プラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も調査をすることができます。
不動産評価に強い専門家に相談すべき理由
1 不動産の評価とは

例えば、コンビニで売られている飲み物や、スーパーで売られている野菜など、世の中で売られている多くの商品には、通常、値段がつけられます。
しかし、その多くは、全く同じ商品が大量生産されたものであり、値段がある程度決まっています。
他方、土地・建物といった不動産は、同じものが存在しないという特殊性があるため、決まった値段というものがありません。
もちろん、不動産にも相場といわれるものがあり、例えば、京都駅のような主要駅の近くの物件は高額になるといった傾向はあります。
しかし、極論をいうと、売主と買主が合意すれば、相場の金額とは関係なく、合意した金額が、その不動産の値段となります。
もし、不動産を売却することになれば、ある程度その市場価値が分かるのですが、相続で取得した場合は、実際に売るとは限りません。
そこで、様々な事情から、その価値を予測する必要があります。
このように、実際に売ることなく、不動産の価値を決めることを、不動産の評価と言います。
2 生前対策で不動産評価が必要な理由
生前対策は、誰にどれくらいの遺産を相続させるかということが、大きなテーマです。
相続人の間で、あまりに不平等があると、揉めごとが起きてしまう可能性があります。
例えば、実家を長男に相続させ、預貯金を二男に相続させるという遺言書を作成した場合、遺言書作成時は、実家が新しく、3000万円の価値があったものの、相続時には実家の価値が1000万円まで下がっているということも十分あり得ます。
そこで、不動産の評価額を決め、その他の預貯金や株式とのバランスを見て、誰にどの遺産を相続させるかを決める必要があります。
3 遺産を分ける際に不動産評価が必要な理由
遺産を分ける際には、遺言書が無い限り、法律で定められた割合で分けることが原則です。
その際、遺産が預貯金ばかりであれば分け方には困りませんが、土地や建物がある場合、分け方で揉めることがあります。
特に、一部の相続人が不動産を相続する代わりに、不動産の価値評価に基づいて、ほかの相続人に対して金銭による補償を行う代償分割を実施する場合、現実に売却することなく、金銭による清算を行うので、不動産の評価が極めて重要になります。
4 遺留分侵害額請求をする際に不動産評価が必要な理由
相続人の間で遺留分侵害額請求が行われる場合にも、不動産の評価が問題になります。
例えば、遺言によって遺留分を侵害する不動産の贈与が行われた場合、遺留分侵害額の算定は、相続財産全体の金額と不動産の価値によります。
そのため、不動産の価値をどのように評価するかによって、遺留分侵害額が大きく左右されるのです。
また、被相続人から相続人に対して、特別受益に当たる不動産の生前贈与が行われていた場合には、その価額が相続財産に持ち戻されることになるので、やはり不動産の評価が重要になります。
5 不動産評価に強い専門家に相談することが大切です
上記で説明したとおり、生前対策の時も、遺産を分ける場面でも、不動産の評価は不可欠です。
もし、不動産評価に不慣れな専門家に依頼して、その評価が不適切なものになってしまった場合、結果的に親族が揉めてしまったり、取得できるはずであった遺産を取得できなくなってしまったりするなどのリスクがあります。
そのため、相続について相談する場合は、不動産評価に強い専門家にご相談することをおすすめいたします。
私たちは、不動産評価の対応も得意としていますので、京都で相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
相続のお悩みの相談先
1 相続のお悩み

相続に関する悩みは、複雑で何が問題であるかを整理できないようなこともあり、誰にどのように相談をしたらよいのか、迷うことも少なくありません。
たとえば、長年にわたり相続登記がされていない、相続でどのくらい相続税がかかるのかどうか知りたい、自分はある不動産が欲しい/欲しくない、不動産の評価が分からない、亡くなった人にどのような財産があるのか分からない、他の相続人と疎遠で連絡を取ることができない、他の相続人と関係がよくない・・など、実に様々な悩みがあります。
このような場合、専門家に相談することで、問題を整理・分析し、道筋を立てていくことができるようになります。
的確なアドバイスを受けることで、相続を適切に進めることができるようになるかと思いますので、まずはお早めにご相談ください。
2 相談先について
相続に関する専門家としては、法律の専門家や税務の専門家が挙げられますが、そもそも相続をあまり扱っていないところもあるので、まずはホームページなどで確認するとよいです。
ではどのような専門家に相談したらよいのかというと、それぞれが扱える内容は、おおよそ、次のようなところとなります。
弁護士は、相続全般について相談できます。
当事者の代理人として交渉することができ、調停・訴訟の手続きも任せることができます。
これに対し、司法書士は、不動産登記のほか、争いのない相続手続きについて相談することができます。
行政書士は、官公署に提出する書面や権利義務に関する書面を作成するほか、書面作成に関して相談をすることができます。
税理士は、相続税申告や所得税の準確定申告などについて相談できます。
お悩みの内容に応じて、それに対応してくれる専門家に相談するか、専門家同士が連携しているところに相談するのがおすすめです。
3 相続について弁護士に相談するメリット
親族ともめたくない、トラブルになっては困る、あえて裁判までやりたくない等の気持ちから、弁護士に相続について相談することをためらう方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、なんでも裁判をやることがよいとは限りません。
しかし、いざとなったら必要な法的手続きをとれるということから、かえって冷静に話し合いが進むということもあります。
また、扱える範囲が限定されていないため、全体的な観点から解決をすることができるという点が強みともいえます。
相続の専門家に相談する流れ
1 相続の専門家の探し方

相続は、法律や税金が複雑に絡み合う、難しい分野です。
そのため、相続についてお悩みの方は、専門家に相談することをおすすめします。
専門家の探し方として、知人のつてをたどったり、テレビや電車の広告から専門家を探したりする方法がありますが、現在はインターネットを活用して専門家を探す方が多くなっています。
例えば、特定の地域で相続についての専門家を探す場合は、「地域名 相続」といったキーワードで検索すると、探しやすいかと思います。
また、専門家を選ぶポイントとして、複数の分野の専門家が連携しているかどうかが重要です。
相続は、法律や税金が絡み合う分野ということもあって、初めは法律の専門家に相談しており、途中で税金の専門家にも相談する必要が生じるということも珍しくないためです。
そこで、法律の専門家、税金の専門家などが、同じ事務所に在籍していれば、専門家同士で連携がとれるため、それぞれの専門家に何度も同じ説明をしなくてもよくなります。
私たちは、法律・税金等の専門家が必要時に連携してご依頼をお受けできる体制を整えていますので、相談内容を説明し直す必要はありません。
2 事務所に電話やメールで連絡する
多くの事務所では、事前に予約をした上で、後日、専門家と相談するという流れになります。
そのため、まずは事務所に電話やメールをして相談の予約をします。
その際、ある程度相談内容を伝えておくと、相談当日の話がスムーズに進みます。
特に、相談料が必要な事務所に相談する場合は、事前に相談内容を伝えておくと、時間が延びて相談料が高額になることを防ぐことができます。
相談料は、30分あたり何円や、時間に関係なく1件あたり何円という設定がされるなど、事務所によって様々です。
もっとも、相談料が無料の事務所であれば、このような心配は不要です。
当事務所は、相続に関するご相談は原則として無料になっているため、お気軽にご相談いただけます。
3 相談当日の流れ
⑴ 事務所での相談の場合
専門家は、資料をもとに今後の見通しを立てるため、事務所に資料を持っていくとより充実した相談が可能です。
相続の場合は、家系図や遺産の資料などがあると、より具体的なアドバイスが可能になります。
また、相談の際は、どんな点に不安や不満があるのかも、しっかりと専門家に伝えるとよいです。
⑵ 電話での相談の場合
最近は、電話で相談を受け付けている事務所が増えてきました。
電話での相談の場合、資料の内容をお電話でお伝えいただく必要があるため、お手元に資料を用意した上で電話をすると、相談がスムーズに進みます。
また、事前に事務所へ資料の写しを郵送しておくと、事務所で実際に対面している場合と同じような形で相談を進めることができます。
4 相談後の流れ
相談の上、専門家に依頼することになれば、その場で契約書を交わしたり、後日契約書を郵送したりすることになります。
もちろん、その場ですぐに契約する必要はありませんので、一度ゆっくり考え、後日に再度相談するということも可能です。
相続が得意な専門家の特徴
1 相続が得意な専門家には特徴があります

相続を集中的に取り扱っている専門家は、様々な分野を手広く取り扱う専門家と比較すると、相続に関する手続きや、親族間の揉め事の解決において、多くの実績があります。
相続が得意な専門家には、その実績がある分、いくつかの特徴があります。
2 相続に関する期限を熟知している
相続に関する手続きには、期限が定められているものが多くあります。
その期限を守らなかった場合、余計な税金を支払うことになったり、本来得ることができたはずの財産を失うことになってしまったりするなど、様々な不利益が発生することがあります。
期限は相続手続きごとに異なり、例えば、市役所への届出が1~2週間、相続放棄が3か月、準確定申告が4か月となっています。
そのため、相続を扱う上では、常に期限の問題を意識して、限られた時間の中でスケジュールを組み立てなければなりません。
何をいつまでに行わなければいけないのかを調べることに時間を取られ、手続き自体の進捗が遅れてしまうと、期限が間近に迫り焦ることになりかねません。
相続を得意とする専門家であれば、相続に関する期限を熟知しており、期限を守らなかったことによる不利益を避けるために、適切なアドバイスをすることができます。
また、専門家に手続きを任せてしまうことも可能です。
そうすることで、ご自身で対応する手間を軽減できますし、相続手続きを効率よく正確に進めてもらうことができるため、スムーズに相続を行えることが期待できます。
3 相続に関係する税金に詳しい
相続の手続きと切っても切り離せないのが、税金です。
しかし、手続きにも税金にも詳しい専門家というのはあまり多くありません。
相続手続きを弁護士に、税金は税理士にとバラバラに依頼してしまうと、全体を見据えたスケジュールが立てられず、思わぬ落とし穴にはまって余計な税金を支払ってしまうこともあります。
この点、相続を得意とする専門家であれば、必然的に税金にも詳しくなります。
特に、税金に関する法律は、毎年のように変わるため、相続を集中的に取り扱っている専門家であれば、税法の改正にも敏感です。
相続を中心に扱っている専門家であれば、税金面で税務署からの指摘などを受けたりしないよう、最新の法改正をチェックしつつ、手続きを進めることができます。
4 相続に関する最新の判例や裁判例に詳しい
相続は、家庭ごとに事情が異なるため、それぞれの事情に応じた様々な判例や裁判例があります。
その結果、相続全般に影響を与えるような、新しい重要判決がでることもあります。
複数の分野を広く扱う専門家は、各分野の最新の判例や裁判例をチェックしなければならないため、検討しなければならない事案も多くなり、十分に研究ができない可能性があります。
しかし、相続を集中的に取り扱っている専門家であれば、相続に関する最新判例や裁判例を研究する時間を取りやすく、その動向に詳しいといえます。
相続に関するお役立ち情報の掲載
相続の専門家を探している方や、相続についての情報を集めている方の参考となるような情報を掲載しています。今後も更新していきますので、参考にご覧ください。